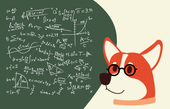ドッグフードの袋にある「オメガ3」の文字、気になっていませんか。オメガ3は、からだが自分では作れない大切な油で、魚や海の藻、アマニなどに多く含まれます。役割を一言でいうと“炎症を抑える消化器”。一方、腸内フローラ(腸の中の菌のなかま)は炎の延焼を防ぐ“耐火壁”です。
オメガ3と腸内フローラが手を組むと、皮膚・免疫・便の安定がじわっと整いやすくなります。本記事では、オメガ3の基礎から、腸活との相乗、フードの選び方を詳しく解説します。
1. まずはここから:オメガ3ってなに?腸内フローラってだれ?
ドッグフードの袋でよく見る「オメガ3」は、体では作れない“良い油”。魚や海の藻、アマニなどに多く、からだの“炎症”を静かに消火する方向に働きます。いっぽう「腸内フローラ」は腸に住む菌のチーム。食物繊維を食べて腸の壁=バリアを守る合図を作る、いわば“耐火壁”。
この二人が同じ方向を向くと、皮膚・免疫・便の“ぶれ”が小さくなり、毎日の調子がじわっと安定。むずかしい言葉は使いません。消化器(オメガ3)と耐火壁(腸内フローラ)――このイメージを持って読み進めてください。
オメガ3=“炎症の勢いを弱める消化器”
オメガ3にはEPA・DHA(魚や藻)とαリノレン酸(植物)の3兄弟がいます。体がすぐ使えるのはEPA・DHA、植物のαリノレン酸は“下ごしらえ用”で、体の中で一部だけEPA・DHAに変わります。
オメガ3のすごいところは、からだの“ピリピリ”をおだやかにする方向へ合図を出すこと。皮膚のコンディションや関節のこわばり、心と脳の毎日に関わります。フードの原材料に「魚油」「藻油」などがあれば、まずは一歩前進のサインです。
腸内フローラ=“炎症の広がりを防ぐ耐火壁”
腸内フローラは、食物繊維(イヌリンなど)を原料に短鎖脂肪酸という“防火コーティング(燃え広がりにくくする層)”をつくり、腸のタイトジャンクション(細胞のすき間の“耐火シーリング”)を補修します。さらに粘膜IgAという“初期消火隊”が表面の小さな火種を素早く鎮めます。
こうして壁の中身が厚く、すき間もふさがった家は延焼しにくい。腸が落ち着けば、全身の“火の勢い”も弱まり、皮膚・便・気分のくすぶりが鎮まりやすくなります。
2人が手を組むと何が起きる?
オメガ3(消火器/霧)と腸内フローラ(耐火壁/防火扉)が同時に働くと、「火種が広がりにくい×燃えてもすぐ鎮火」の二段構えになります。腸の“耐火シーリング(タイトジャンクション)”を補修しながら、炎の勢いを落とすイメージ。これが皮膚・免疫・便のくすぶりを鎮め、季節の変わり目や環境の変化にも延焼しにくい土台をつくります。ポイントは“少しずつ重ねる”。いきなり大量ではなく、食物繊維と善玉菌を少量から、EPA/DHAも段階的に——やさしく積み上げるほど、からだは素直に応えてくれます。
2. 相乗のルールは3つだけ
相乗といっても難しくありません。ルールはたった3つ。(1)土台づくり:食物繊維で腸が動ける環境をつくる。(2)合図を足す:善玉菌(乳酸菌・ビフィズス菌など)で「こっちだよ」と背中を押す。(3)消化活動:EPA・DHAで炎症の勢いを静める。順番に少しずつ重ねると、腸→免疫→皮膚のラインが同じ方向に揃い、手ごたえが出やすくなります。どれか一つを全開にするより、3つを“ちょい足し”で並べるのが近道です。
土台:食物繊維(イヌリンなど)で補強
耐火壁(腸内フローラ)は、材料がないと補強できません。イヌリンやフラクトオリゴ糖などの発酵性食物繊維は、菌たちの“大好物=耐火材の原料”。これで短鎖脂肪酸という“防火コーティング”が増え、腸のタイトジャンクション(細胞のすき間の“耐火シーリング”)が補修されます。いきなり厚塗りはNG。量が多すぎるとガス・軟便の火種に。まずは“ひとさじ”から、7〜10日で段階的に厚みを出すのがコツです。ラベルでは原材料名の上位にイヌリン/FOSなどの繊維源があるかをチェックする習慣をつけましょう。
合図:善玉菌(乳酸菌・ビフィズス菌など)で背中をポン
菌の“からだ”や“作る物質”は腸に小さな合図を届け、粘膜の見張り(IgA)やバリアづくりを後押しします。生菌・不活化の形は問わず、要は“腸にやさしい合図”を増やすこと。食物繊維の土台と組み合わせると定番の相乗に。少量から始め、便・食欲・元気を見ながら微調整。EPA・DHAの“音量調整”と合わせると、静けさの土台が整いやすくなります。
消化:EPA・DHAで“炎症の勢い”をしずめる
即戦力のオメガ3(EPA/DHA)は、炎症の火力を落とす“霧の消火器”。皮膚・関節・心と脳の毎日を静かに支えてくれます。植物のαリノレン酸も大切ですが、EPA/DHAへの変換はわずか。まずは魚や藻のオメガ3を“ちょい足し”するのが現実的です。土台(食物繊維=耐火材)+合図(善玉菌=初期消火隊)+消火(EPA/DHA)――この3ピースがそろうと、からだのくすぶりは驚くほどすっと鎮まります。
3.原材料の見分けクイズ「このラベル、どっちが良い?」
同じ「オメガ3入り」でも中身は大違い。実物の油(魚油・藻油・アマニ油)と、香り付け(フィッシュフレーバー)は別物です。前者はオメガ3を増やしますが、後者は食いつき目的。さらに“数字”があると安心。「オメガ3◯%」「EPA/DHA◯mg/100g」などの表記があると、体重に合わせた目安が計算できます。ここでは“実物の油+数字+酸化対策”の三拍子を、ラベルから見抜く目を育てましょう。
魚油/藻油/アマニ油の違いをサクッと
魚油=EPA/DHAが直接とれる“即戦力”。藻油=DHA中心、魚が苦手な子にも使いやすい。アマニ油・チア油=αリノレン酸中心の“下ごしらえ役”。どれが良い悪いではなく、目的で使い分けるのが正解です。皮膚・関節・シニアケアなら魚油や藻油を少し上めに、日々の維持なら植物由来も上手に併用。原材料の先頭寄りに書かれているほど配合が多い、も覚えておくと役立ちます。
“フィッシュフレーバー”は油じゃない!?
「フレーバー」は香り。オメガ3の量は増えません。ラベルに“フィッシュフレーバー”だけの製品は、オメガ3目的では選びにくい。一方、「サーモンオイル」「アルガル(藻)オイル」など実体のある油はプラス要素。迷ったら“香り”と“実物の油”を見分けることから。ここがクリアになるだけで、選択の精度がぐっと上がります。
オメガ3%/EPA・DHA mg表示の見方
理想は数字で伝えるラベル。「EPA+DHA=◯mg/100g(または◯mg/100kcal)」があれば、給餌量(または1日の摂取カロリー)にかけ算して1日の摂取量が分かります。例:200mg/100gのフードを200g食べるなら約400mg/日。サプリで足す場合は“合算”が基本です。日常の維持はフード側で15〜30 mg/100kcal程度でも十分。狙いがある時期は、EPA+DHAを体重1kgあたり50〜100 mg/日(または30〜60 mg/100kcal相当)に期間限定で近づけ、落ち着いたら維持量へ戻しましょう。表示がない場合は、油の種類と原材料の位置から推測し、少量から様子を見るのが安全です。子犬/妊娠・授乳期、薬や手術前後は獣医に相談を。
4. 量の目安とカンタン暗算
「オメガ3を積極的に取り入れたいときはどれくらいあげればいい?」の答えは、“EPA+DHAで体重1kgあたり50〜100mg/日”が目安ゾーン。幅があるのは体質や目的が違うから。皮膚/関節ケアは上寄り、日々の維持は下寄りから。そして最重要は“半分スタート”。いきなり満量はお腹がびっくり。7〜10日でスライド導入すれば、体も気持ちもついてきます。数値は目安。最終判断は愛犬の様子です。便・毛づや・食べ方(食欲)・体重を2〜4週間見て調整しましょう。
体重1kgあたり何mg?家の子はどのくらい?
暗算は簡単。“体重×50〜100”。3kgなら150〜300mg、10kgなら500〜1,000mg。これはEPA+DHAを“狙いがある時期(皮膚・関節など)”に目指す目安です。日常の維持はもう少し低め(体重×10〜20mg/日、=フードで15〜30 mg/100kcal相当)でも十分。これを一日の合計として、フードとサプリの“合算”で調整します。体質によっては少しの量で十分な子も。観察メモ(便・毛づや・元気)を1行でよいので残すと、最適量が見つかるスピードが段違いに上がります。子犬/妊娠・授乳期、薬や手術前後は獣医の指示を最優先に。
すでに入っている分との“合算”のしかた
フードに「EPA/DHA◯mg/100g」とあれば、給餌量でかけ算→一日の摂取量が算出できます。そこにサプリを足すなら“合算”。表示がない場合は、魚油/藻油が上位に書かれているかを目安にし、サプリは少量から。合算の習慣があれば“入れすぎ→お腹ゆるむ”の落とし穴を回避できます。計算はメモ帳アプリでもOK。続けやすさが一番です。
いきなり増やさない、7〜10日の慣らし方
体は急な変化が苦手。初日は目標量の1/2、3日目に2/3、1週間で満量――これが“スライド導入”。便がゆるんだら一段階戻し、数日安定させて再トライ。脂質の総量(カロリー)も合わせて見直すと、お腹が落ち着きやすい。小さなブレーキは失敗ではなく、最短ルートの印。焦らず、やさしく、でOKです。
5. ニオイでわかる?酸化チェック
オメガ3は新鮮さが命。空気や光で“酸化(劣化)”すると、金属っぽいツンとしたにおいが出たり、犬が急に食べ渋ったり。酸化した油は目的の働きをしにくく、お腹の負担になることも。だから選ぶ段階で“小分け・遮光・抗酸化剤(ビタミンE等)”をチェック。開封後はしっかり密閉し、冷暗所で保管。においの変化は最高のセンサー。鼻で守る、オメガ3の価値。
酸化ってなに?開封後はここに注意
酸化は“油が空気でサビる”現象。開封した瞬間から少しずつ進みます。注意は①密閉(空気を遮断)②遮光(直射日光/高温多湿を避ける)③時間(開封後1〜2か月で使い切る)。スプーンや手は清潔に、袋の口はこまめに閉める――このひと手間で、オメガ3の鮮度はぐっと守れます。においが変だと感じたら、無理に使わない勇気も大切です。
小分け・遮光・ビタミンEの“3種の守り”
理想の三点セットは“小袋×遮光袋×ビタミンE(ミックストコフェロール)”。小袋なら空気に触れる回数が減り、遮光で光ダメージをブロック。ビタミンEは“油のボディーガード”。原材料や成分に記載があるかを確認。詰め替えるなら遮光容器で、空気を抜いて保存。開封日を書いておくと、使い切りのリズムも作りやすいですよ。
6. 目的別の使い分けミニガイド
目的が変われば“攻め方”も変わります。皮膚・被毛、関節/シニア、お腹と気分――どれを優先するかで、魚油/藻油の比率や量、合わせる腸活素材が少し違う。共通の土台は、食物繊維(イヌリンなど)+善玉菌(乳酸菌・ビフィズス菌)の相乗に、EPA/DHAの“消化活動”を重ねること。少量から、観察して、微調整。これさえ守れば、最適解に近づきます。
皮膚・毛づや/関節・シニア/お腹と気分
皮膚・毛づや:魚油/藻油を“やや上め”にし、保湿ケアと並走。関節・シニア:体重管理+EPA/DHAで“こわばり期”に備える。緑イ貝などの関節素材とも相性良。お腹と気分:EPA/DHAで炎症の音量を下げ、イヌリン+善玉菌で腸の見張りを増やす。睡眠や落ち着きの“底”が整いやすくなります。どの目的でも、無理をせず“続く量”を。
腸活と合わせると“ぶれ”が小さくなる理由
耐火材(繊維)で壁の中身を厚くしてバリア強化、善玉菌の合図で“初期消火隊(IgA)”が増えて巡回UP、EPA/DHAという“霧の消火器”で火力ダウン。三段重ねで「入れない(耐火シーリングで隙間をふさぐ)・延焼させない(防火コーティング)・鎮める(消火)」が同時に進みます。どれか一つだけだと別の穴が残りがち。三つを少しずつ重ねるほど、皮膚もお腹も“ふだん基準”が上がって、くすぶりにくい体に。派手ではないけれど、続けるほど効いてくる——それが相乗の底力です。
7. よくある誤解を1分で
誤解1「アマニ油だけでOK?」→αリノレン酸は大切ですが、EPA/DHAへの変換はわずか。魚・藻の“即戦力”をちょい足しで。
誤解2「多いほど良い」→入れすぎは軟便・体重増の原因に。適量と慣らしが鍵。
誤解3「薬や手術前でも気にしなくていい」→抗凝固薬や手術前後は獣医に相談。3つを押さえるだけで、つまずきの大半は回避できます。
アマニ油だけでOK?(変換の壁)
アマニやチアの油に多いαリノレン酸は良い油ですが、“EPA/DHAの代替”にはなりにくいのが現実。体内での変換は少ないため、必要量をまかなうのは難しいことが多いです。解決策はシンプル。“アマニ+魚(または藻)”の両輪に。植物はサポート、魚/藻は即戦力。どちらも“少量から慣らす”で、お腹にやさしく続けられます。
たくさん入れれば入れるほど良い?(上限と下痢)
油は“量と鮮度”が命。過剰は軟便・嘔吐・体重増の原因になります。目安はEPA+DHAで体重1kgあたり50〜100mg/日。まず半量から、便・毛づや・食いつきを見ながら少しずつ。においが変なら無理に与えない。“適量×継続”が、毎日の安定をつくります。
薬や手術前は大丈夫?(獣医に相談)
抗凝固薬との併用や手術前後は、オメガ3の量に配慮が必要な場合があります。自己判断は避け、かかりつけ獣医に相談を。療法食と併用する際も、油量やカロリー、目的に合うかを確認。相談すること自体が最強の安全策です。
モモまるの紹介
オメガ3の弱点である“酸化”にもばっちり対応、作りたてを-40℃のショックフリーザーで瞬間冷凍し、ビタミンEで配慮。必要量だけ取り出してすばやく密封→冷凍に戻す運用で、鮮度を保ちやすい設計です。毎日の主食として続けやすく、必要な時だけEPA/DHAを“ちょい足し”できる柔軟さも備えています。\n ","contentAlignProduct":"Left","infoProduct":{"id":"gid://shopify/Product/6838310764676","title":"モモまる 国産 手作りドッグフード 総合栄養食 腸活 免疫力","currencyCode":"JPY","amountMax":"2100.0","amountMin":"1100.0","price":"1100","compareAtPrice":null,"imagesUrl":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/0589/1761/7796/files/1_632651ec-c746-423e-942a-1d5d748f8d7f.png?v=1757786412&width=600","urlStore":"/products/%E5%86%B7%E5%87%8D%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%A2%E3%83%A2%E3%81%BE%E3%82%8B","altImage":""},"colorDiscount":{"hue":356,"saturation":0.74,"brightness":1},"colorTitle":{"hue":213,"brightness":0.83,"saturation":1},"colorPrice":{"hue":0,"saturation":0,"brightness":1,"alpha":1},"cssContent":"","activeDecimals":false,"decimalsPrice":2,"isRemoveBranding":true,"hidden":false,"locked":false,"blockName":"Text and product","componentId":"undefined"}
モモまるは、毎日の主食で「オメガ3」と「腸活(食物繊維+善玉菌素材)」を無理なく両立できるように設計しました。実はAAFCOの成犬維持ではEPA・DHAの必須規定はありませんが、NRCの栄養知見を参考にオメガ3を配合し、脂肪酸バランス(n-6:n-3≒5:1、自社分析)にも配慮。DHAを含み、EPA+DHAは約25 mg/100g(約20 mg/100kcal、第三者機関分析値、as-fed)です。
オメガ3の弱点である“酸化”にもばっちり対応、作りたてを-40℃のショックフリーザーで瞬間冷凍し、ビタミンEで配慮。必要量だけ取り出してすばやく密封→冷凍に戻す運用で、鮮度を保ちやすい設計です。毎日の主食として続けやすく、必要な時だけEPA/DHAを“ちょい足し”できる柔軟さも備えています。
まとめ
オメガ3は“霧の消火器”。腸内フローラは“耐火壁と初期消火隊”。この二人が手を組むと、皮膚・免疫・便のくすぶりが鎮まり、季節の変わり目や環境変化でも延焼しにくい土台ができます。選び方は「実物の油(魚/藻/アマニ)」「数字のあるラベル(オメガ3%/EPA・DHA mg)」「酸化対策(小分け・遮光・ビタミンE)」。与え方は「体重目安(EPA+DHA 50〜100mg/kg/日)」「合算(フード+サプリ)」「半分スタート(7〜10日で慣らす)」。そして腸活(食物繊維+善玉菌)を重ね、耐火材と巡回を少しずつ増やす。今日のひとさじが明日の“燃え広がりにくいからだ”へ——無理なく、楽しく、続けていきましょう。
参考文献
オメガ3(犬・獣医領域の総説/臨床)
- Bauer JE. Therapeutic use of fish oils in companion animals. J Am Vet Med Assoc. 2011;239(11):1441-1451.
https://avmajournals.avma.org/doi/10.2460/javma.239.11.1441 - Roush JK, et al. Omega-3 fatty acid supplementation in dogs with osteoarthritis. J Am Vet Med Assoc. 2010;236(1):59-66.
https://avmajournals.avma.org/doi/10.2460/javma.236.1.59 - Calder PC. Marine omega-3 fatty acids and inflammation: from micro to macro. Proc Nutr Soc. 2015;74(3):236-251.
https://doi.org/10.1017/S0029665114001574
オメガ3と腸内フローラの関係
- Watson H, et al. A randomised trial of the effect of omega‑3 on the human gut microbiota. Gut. 2018;67:1974–1983.
https://gut.bmj.com/content/67/11/1974 - Menni C, et al. Gut microbiome diversity and high serum n-3 PUFAs. Sci Rep. 2017;7:11079.
https://www.nature.com/articles/s41598-017-10382-2